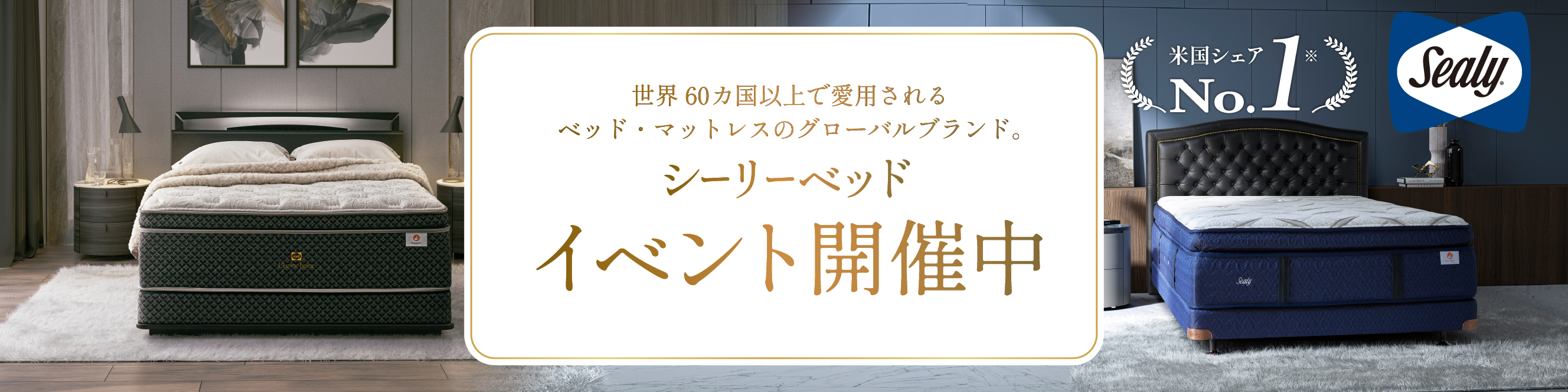.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
畳にマットレス直置きは大丈夫?湿気・カビ対策と正しい寝具選び
公開日:2025.06.29(Sun)
和室でもマットレスで寝たいけれど、畳に直接置いて大丈夫なのか心配になりますよね。実は、畳の上にマットレスを敷きっぱなしにすると湿気がたまって、カビが生える可能性があるのです。
とはいえ、毎日マットレスを上げ下ろしするのは大変です。この記事では、畳の上でマットレスを快適に使うための方法をわかりやすく説明します。カビ対策や湿気を防ぐ方法、マットレスの選び方、すのこやベッドフレームの使い方まで、和室で安心してマットレスを使うコツをお教えします。
畳にマットレスを直置きするとどうなる?
湿気がたまってカビが生える
人は寝ている間に、コップ一杯分もの汗をかきます。その汗がマットレスの中や下にたまって湿気になります。
畳は湿気を吸い取る力がありますが、マットレスで覆われていると風通しが悪くなります。畳が処理できる量を超えた湿気がたまると、カビが生えてしまいます。
湿気の多い場所はダニも増えやすくなります。髪の毛や皮膚のかすをエサにして、どんどん増えていきます。カビやダニはアレルギーや喘息の原因になることもあるので注意が必要です。
マットレスが傷みやすくなる
湿気を含んだマットレスは、中のウレタンフォームなどが傷みやすくなります。十分に乾かない状態が続くと、マットレスのクッション性がなくなって寝心地が悪くなります。
カビが生えると黒い斑点や嫌な臭いが発生して、とても不衛生です。そんなマットレスで寝続けるのは健康にも良くありません。
畳も傷んでしまう
厚くて重いマットレスを畳に直接置くと、畳に圧力がかかってへこんだり跡がついたりします。特に重いマットレスは、畳の一部分に大きな力がかかるので要注意です。
また、マットレスを敷きっぱなしにして湿気がたまると、畳自体にもカビが生えることがあります。畳にカビが生えると、見た目も悪くなりますし、畳を交換する必要が出てくることもあります。
ホコリの問題も
床に近い場所にはホコリがたまりやすく、マットレスを直接置くとその裏にホコリや汚れがつきやすくなります。ホコリにはダニの死骸やカビの胞子が含まれているので、吸い込むとアレルギーを起こす可能性があります。
このように、畳にマットレスを直接置くと「湿気・カビ」「ダニ・ホコリ」「マットレスの劣化」「畳の傷み」という問題が起こります。できるだけ直置きは避けて、ベッドフレームの上で使うのがおすすめです。
畳に直置きする場合の湿気・カビ対策
どうしても和室にマットレスを直接敷かなければならない場合は、しっかりと湿気対策・カビ対策をすることが大切です。
毎日マットレスを立てて風を通す
直置きで最も大切なのは、敷きっぱなしにしないことです。朝起きたら、マットレスを畳から離して壁に立てかけたり、折り畳んだりして、裏面に空気を当てましょう。
晴れた日は窓を開けて風通しを良くして、マットレスと畳にたまった湿気を飛ばします。これは布団を干すのと同じように、直置きマットレスでも必ず必要なお手入れです。
「毎日片付けるのは大変...」という場合でも、少なくとも週に数回は立てかけて乾燥させるようにしてください。マットレスを動かすのが大変な場合は、取っ手がついているものや折り畳みタイプを選ぶと楽になります。
部屋の換気も同じくらい大切です。マットレスを立てても、部屋の空気自体が湿っていては意味がありません。晴れた日は窓を開けて、新鮮な外の空気と入れ替えましょう。
梅雨や冬で外の空気が湿っている時は、エアコンの除湿機能や除湿機を使って部屋の湿度を下げます。湿度は60%以下に保てれば、カビの繁殖を抑えることができます。
除湿シートをマットレスの下に敷く
市販の除湿シート(吸湿シート)を使うのも効果的です。シリカゲルや炭などの素材でできていて、敷くだけでマットレスの下にたまった水分を吸い取ってくれます。
使い方は簡単で、畳とマットレスの間にシートを広げて敷くだけです。シートが湿気を吸い取ってくれるので、マットレスや畳への湿気を減らすことができます。
ただし、除湿シートも万能ではありません。吸い取れる水分の量には限界があります。製品に書かれている使用期間を守って、定期的にシート自体を天日干しで乾燥させるか、新しいものと交換してください。
除湿シートはマットレスの大きさに合ったサイズを選びます。シングルマットレス全体をカバーできるものを使わないと、シートからはみ出た部分に湿気が集中してしまいます。
布団乾燥機や除湿機を使う
布団乾燥機を使うのもおすすめです。本来は布団に温風を送って乾燥させる家電ですが、マットレスにも使えます。立てかけたマットレスに風を当てたり、折り畳みマットレスを広げて乾燥させたりすると、中までしっかり乾かすことができます。
梅雨など太陽に干せない時期には特に重宝します。ただし、ウレタン製マットレスの場合は温度が高くなりすぎないよう注意して、メーカーが推奨する温度・時間を守ってください。
除湿機も役立ちます。室内の湿度を下げることがカビ対策には欠かせません。梅雨時や結露しやすい冬は、寝ている間や起きた後に除湿機を動かして部屋全体の湿度を管理しましょう。エアコンの除湿機能でも代用できます。
扇風機やサーキュレーターで部屋の空気を循環させると、湿った空気が一箇所にたまりにくくなります。エアコンと一緒に使って風を動かす工夫も効果的です。
すのこや通気マットで隙間を作る
できれば、マットレスと畳の間に空気の通り道を作ると効果的です。「すのこマット」や「通気マット」を使って、床とマットレスの間に隙間を作る方法があります。
すのこ状の板を敷くことで空気が通りやすくなります。折り畳み式の桐すのこボードや樹脂製のマットなど、様々な商品があります。
ただし、すのこを使えば完璧というわけではありません。床からの高さが低いため、思ったほど通気の効果が得られない場合もあります。すのこを敷いても、定期的な換気・乾燥は必要です。
また、木製すのこを畳に直接敷くと、硬くて狭い部分が畳に当たって傷つけてしまう可能性もあります。すのこを使う場合は、すのこと畳の間に薄いカーペットやコルクマットを挟むか、すのこの角にフェルトを貼って畳を保護しましょう。
これらの対策を組み合わせれば、畳直置きによる湿気・カビのリスクを大きく減らすことができます。「毎日換気」「吸湿アイテム活用」「家電による乾燥」「通気スペース確保」の四つがポイントです。
畳の上で使うマットレスの選び方
畳に直接マットレスを置く場合は、マットレス自体の選び方も重要です。床に直接敷くことを考えて作られたマットレスを選べば、湿気対策や寝心地の面でメリットがあります。
通気性の良い素材・構造を選ぶ
マットレスにはスプリング(コイル)式、ウレタンフォーム、ラテックスフォーム、ポリエステルファイバーなど色々な種類がありますが、直置きには通気性の高いものが向いています。
例えば、中が空洞になっているポケットコイルマットレスや、高反発ファイバー素材のマットレスは、空気の通り道が多くて湿気がたまりにくいです。一方、低反発ウレタンのように密度が高くて通気しにくい素材は、湿気をためこみやすいので避けた方が良いでしょう。
ただし注意したいのは、コイルスプリングのマットレスは通気性は良いもののとても重いことです。シングルサイズでも20kg前後もあり、床から持ち上げたり立てかけたりするのが大変です。その重さで畳にかかる負担も大きく、直置きには向いていません。
そこでおすすめなのが、コイルを使わないタイプのマットレスです。高反発ウレタンやラテックスフォーム、樹脂ファイバー素材のマットレスなら、軽くて通気性にも配慮された製品が多くあります。
例えば昭和西川の「ムアツふとん」はウレタンフォーム製で通気性に優れ、畳の上に1枚で敷いて使える設計です。エアウィーヴやブレスエアーなどの樹脂ファイバーマットレスは中がほぼ空気でできており、水で洗えるほど通気性・速乾性に優れているので直置きに向いています。
十分な厚みと硬さを確保する
直置きで快適に眠るには、マットレスの厚みと硬さのバランスも重要です。薄すぎるマットレスだと体が沈み込んで、腰や肩が床について痛くなってしまいます。
一般的に、床に敷いて使うなら10cm以上の厚みが望ましいとされています。特に体重のある方や横向きで寝る方は、薄いものでは底つき感が出やすくなります。余裕があれば15~20cm程度の厚みがあるマットレスを選べば安心です。
ただし、単に厚ければ良いというものでもありません。大切なのは体圧分散と反発力です。極端に柔らかすぎるマットレスでは、体が沈み込みすぎて厚みがあっても底についてしまいます。逆に硬すぎるマットレスは薄くても底つきしにくい半面、体の一部に圧力が集中して痛くなることもあります。
理想は、適度な反発力で体を支えながら、局所的な圧迫を和らげてくれるバランスの良いマットレスです。実際に寝転がってみて、自分の体格で底つきしないか、寝返りはしやすいか確認すると良いでしょう。
軽さ・扱いやすさも大切
畳直置きを前提とするなら、マットレスの重さや形も重要なポイントです。毎日の陰干しや掃除のために動かす必要があるので、軽い方が断然扱いやすいのです。
シングルサイズで5~8kg程度までなら一人でも楽に上げ下ろしできます。それより重いものは移動時に引きずって畳を傷つけてしまう恐れもあります。畳を長持ちさせるためにも、できる限り軽いマットレスを選ぶことをおすすめします。
また、折り畳みや分割構造も検討しましょう。三つ折りマットレスなら、使わない日中はコンパクトに畳んで隅に立てかけておけますし、持ち運びも楽です。二分割・三分割できるタイプもあります。これらは掃除の時に一枚ずつ動かせるので便利です。
折り畳みタイプの場合、厚みは若干薄め(8~10cm程度)のものが多いですが、高反発ウレタンなどを使って底つきしないよう工夫されています。「三つ折り10cm厚でも底つき感なく快適だった」という声もありますので、自分の部屋の収納スペースや体格に合わせて検討すると良いでしょう。
最後に、抗菌防臭・防ダニ加工の有無も確認ポイントです。最近のマットレスにはカバー生地に抗菌防臭加工を施したものや、ウレタンに防カビ剤を練り込んだものもあります。これらはカビやダニの繁殖を抑える手助けになります。
ただし、加工があるからといって湿気対策を怠ればカビが発生する可能性はゼロにはなりません。あくまでサポート程度と考えて、基本の除湿・換気は欠かさないようにしましょう。
ベッドフレームやすのこベッドの活用
ここまで直置きの場合の対処法を説明してきましたが、根本的な解決策としてはベッドフレームを使うのがやはり一番確実です。
どうしても床に直接マットレスを置くと湿気のリスクは避けられませんが、ベッドフレームの上で使えば空気の流れが確保されて、カビの心配を大幅に減らせます。和室にベッドという組み合わせに抵抗がある方もいるかもしれませんが、最近は和室に合う低めのデザインやヘッドボードなしタイプのフレームも増えています。
ベッドフレームを使うメリット
ベッドフレームを使う最大のメリットは、マットレスの下に十分な空気の通り道ができることです。フレームは脚がついて高さがあるため、床との間を空気が通り抜けます。これで湿気がたまりにくくなり、マットレス自体も長持ちします。
特に底面がすのこ板やメッシュ構造になっているフレームなら通気性は抜群です。毎日マットレスを立てかけて乾燥させる手間も、大幅に楽になるでしょう。
加えて、ベッドの下に隙間があることで掃除がしやすくなる利点もあります。床に直置きだとマットレスの下の掃除は大変ですが、ベッドならそのままモップや掃除機を差し込んで清掃できます。
睡眠環境としても、床から距離ができることでホコリを吸い込む量が減る効果があります。ホコリは床付近にたまるため、ベッドで少し高い位置で寝る方がきれいな空気を吸いやすいのです。
和室にベッドを置く時の注意点
畳の上にベッドフレームを置く場合、いくつか注意すべき点があります。以下のポイントに気をつけることで、畳を傷めずに快適なベッド生活を送ることができます。
脚の下に保護マットを敷く
ベッドの脚が直接畳に当たると、その部分に強い力がかかって畳がへこんだり裂けたりする恐れがあります。そこで、脚の下には脚用の敷板や保護マットを挟みましょう。
ホームセンターで売っている家具用脚パッド(フェルトシール)やゴム板を貼り付けても構いません。四隅の脚以外に中央にも支柱があるタイプなら、そちらにも忘れず対策してください。
通気性の良い床板を選ぶ
和室に置くベッドフレームは、できるだけ通気性に優れた構造のものを選びましょう。具体的には、床板がすのこ状になっているものや、メッシュ状の布や樹脂で支えるタイプがおすすめです。
通気性が悪い板張りフレームだと、結局マットレスの下に湿気がたまって畳にカビが発生する可能性があります。
接地面の広いデザインを選ぶ
フレームの脚や土台部分は、なるべく接地面積の広いものを選びましょう。脚が細いと力が一点に集中して畳がへこみやすくなります。太めの脚や、脚なしで板で面として支えるローベッドタイプなど、力が分散する設計が理想です。
動かす時は引きずらない
和室でベッドを移動・設置する時は、絶対に畳の上を引きずらないように注意しましょう。重いベッドを引きずると畳に深い傷が入ってしまいます。
移動させる際は一度マットレスを降ろして、できれば二人以上でベッド本体を持ち上げて運ぶのがベストです。難しい場合は、脚の下に毛布や厚手の布を敷いて滑らせるように動かすと摩擦を軽減できます。
壁から少し離して配置する
ベッドを設置する際、壁にぴったりつけないことも大切です。壁との隙間が全くないと、マットレス側面や壁面の通気が悪くなって、その間にカビが発生しやすくなります。
10cm程度で構いませんので壁とベッドの間に隙間を空けて、空気の通り道を作りましょう。これでベッド周辺の湿度がたまりにくくなり、部屋の隅の掃除もしやすくなります。
以上の点に気をつければ、和室にベッドを置いても畳や寝具をきれいに保ちやすくなります。
まとめ:和室で快適にマットレスを使うために
畳の上でマットレスをきれいで快適に使うための大切なポイントをまとめました。
基本は直置きを避ける
畳にマットレスを敷きっぱなしにすると湿気がたまってカビやダニの原因になります。健康面・寝心地の面から、できればベッドフレームと一緒に使うのが理想です。
湿気対策を徹底する
やむを得ず直置きする場合は、毎朝の換気・陰干しを習慣にしましょう。除湿シートや布団乾燥機なども使って、常に湿気をためない工夫が大切です。
マットレス選びを工夫する
和室で使うなら通気性に優れた軽いマットレスがおすすめです。厚みは10cm以上、できれば15~20cm程度あると安心です。折り畳み式なら片付けやすさもアップします。
畳を守る工夫をする
直置きの場合もベッド使用時も、畳への負担を考えましょう。すのこや敷板で通気スペースを確保しつつ畳を保護し、ベッドの脚の下には敷物を入れるなどの対策で畳の傷みを防げます。
定期点検とお手入れを忘れずに
マットレスや畳にカビが生えていないか、裏面を時々チェックしましょう。畳は掃除機掛け・乾拭きでホコリを取り除いてきれいに保ちます。異変に早めに気づけば被害も小さく済みます。
和室でもマットレスで快適に眠ることは十分可能ですが、フローリング以上に湿度管理に気を使う必要があります。伝統的な畳文化と現代のマットレスを上手に組み合わせて、心地よい睡眠環境を作っていきましょう。
畳の上でも正しい使い方をすれば、ふかふかのマットレスでぐっすり眠れるはずです。今回紹介したポイントを参考に、ぜひ実践してみてください。
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。